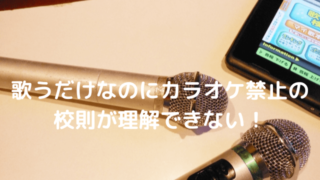日本では、結婚披露宴のクライマックスで新婦が親への感謝の手紙を読むのが恒例となっています。
ここで皆が感動して泣くのが日本の結婚式の定番ですね。
日本の結婚式には涙がつきものというのも、何となくお国柄なのですが。
世界中を見渡せば、日本人からは想像もつかないような形式の結婚式もあるのでしょうから、まあそこはヨシとします。
しかし、ひとつ疑問がありまして。
なぜ親への感謝の手紙を読むのは新婦なのでしょう。

言われてみれば

新郎は読まないね・・

そもそもいつからその儀式やってるのだろう
日本の結婚披露宴のついて、不思議なことがたくさんあるのですが、まずは新婦の手紙についてみておきましょう。
新婦の手紙はいつ始まった
披露宴の定番となった新婦から親への感謝の手紙。
これがいつから始まったのか調べてみると、意外にもさほど古くないことがわかりました。
1990年以降から始まったと言われており、その前は新郎新婦から親へ感謝を込めて花束を贈呈するというのが1980年代頃の定番だったのです。
そして花束贈呈から新婦の感謝の手紙へというのが現在の定番となっていますね。
どこの結婚式場でいつから始まったのか明確にはわかりませんが、1990年から1995年の間には、かなりこの演出が広まったようです。
ある結婚式関連の資料では、「1995年ごろには“両親への手紙”のためのマニュアル本」が出版されており、当時すでに“手紙演出”が定番化しつつあったことを示唆しています。
また、2000年代初頭には、「披露宴で新婦本人が手紙を読む」という今のスタイルが「ほとんど」となる、と記述されている例もあります。
なぜ新婦だけなのか
さて、披露宴のクライマックス、新婦が親への感謝の手紙を読むのは演出として定着したのですが、なぜほとんどが新婦だけなのでしょう。
理由を調べてみました。
歴史的に「花嫁の門出」を強調する文化が強かった
昔の日本の結婚は「家と家を結ぶ」意味が強く、
- 新婦は“嫁ぐ”側(新しい家に入る)
- 新郎は“迎える”側
という構図がありました。
そのため 「育ててくれた家を離れる娘の感謝」 を表す演出として、新婦の手紙が重視されてきました。
つまり、家と家を結ぶという意味の結婚、明治から昭和初期までの家制度の名残というわけです。そんな古臭い意識が1990年代になっても残っていて、それに違和感をおぼえることもなく、この演出が大流行して今では定番となったわけですね。
感情表現の役割分担の慣習
結婚式の伝統演出は、
- 新婦:感謝・家族への想いを言葉で表す
- 新郎:謝辞など儀礼的なあいさつを担当
と分かれていました。
そのため、新婦が個人的で感情的な手紙を読み、新郎は式全体の代表として締めの挨拶をする、というスタイルが一般化しました。
伝統演出というのが適当な表現なのか微妙ではありますが、家制度というものがまだ人々の意識の中に根強く残っているとすれば、家を出る娘の方が感傷的になり、感情に訴えるような演出を担当することになるのでしょう。
和洋ミックスなんでもあり
新婦が親に感謝の手紙を読む演出が生まれた理由が、日本の家制度というものが影響しているのだとしても、そもそも日本の結婚式も披露宴も和洋がミックスされていますよね。
チャペルで結婚式を挙げた後に和装になったり、神前で結婚式を挙げた後に洋装で披露宴をしたり。
日本の一般家庭の結婚式というのは、もともとは神社や教会ではなく家で行うものでした。
実は神前式は古くからの伝統というより、
1910年に大正天皇が行った皇室の神前結婚式をモデルに一般化した比較的新しい儀式です。
そう考えてみると、日本の結婚式というのは伝統を重んじるというよりも、その時代の流行りによって変化してきたと考えるのが自然なのでしょう。
最近では、新婦だけが感謝の手紙を読むのではなく、新郎新婦がそれぞれ手紙を読む演出や、ビデオレターのようなスタイルで二人そろって親や出席しているゲストへ感謝を伝えるという演出も増えているようなので、十年後にはまったく違うスタイルになっているかも知れません。
まとめ
結婚式は伝統的な儀式ではなく、自由に演出を考えてゲストを楽しませるものと考えると、花嫁の手紙というのは、感動の演出としては日本人好みだというのが結論です。